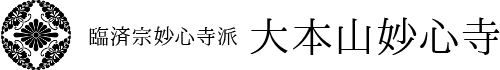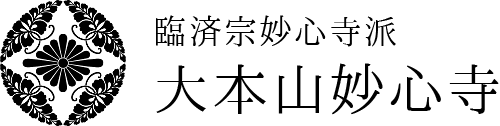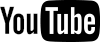ものがみんな熔けているせかい

おとなしくして居(い)ると 花花が咲くのねって 桃子が云う
八木重吉(『貧しき信徒』「花」)
詩の桃子は八木重吉の幼子の名前です。当時、重吉は結核という病魔に冒されていました。季節は春。おとなしく重吉に寄り添っている桃子の心が、静やかに咲いた花花の姿に共鳴しているように感じます。重吉は、子どもの言葉は神の啓示と考え、努めて書き残していたそうです。
禅の祖師方のお悟りも「童心にかえること」に例えられることがあります。童心には損得や利欲を離れた純粋さがありますが、歳を重ねて知識や経験がたまってくると、是非を論じたり、何かと理屈が増えていきます。そんな大人の世界に疲れている時に、子どもの無邪気さ、純真さにふれて頬が緩んだ経験は誰しもがあるのではないでしょうか。
桃子の眼はすんで まっすぐにものを視る 羨ましくってしかたが無い
(「ことば」「子供の眼」)
重吉の詩では「子ども」や「自然」が多く取り上げられ、子どもの眼でものを視ることに憧憬の念を抱きます。桃子はものをありのままに視て、素直に感じたまま、私(人間)と花(植物)のような自他の区別もありません。「こども」という詩の中の一節では、こどもの視るその鮮やかな世界を「ものがみんな熔けているせかい」と表現されています。「熔(よう)」の字を辞書で引けば、「加熱して固体を液体化する」とありました。例えば、地下の岩石が熔けたマグマには流動性があり、さまざまな物質が一つに混ざり合っているように、ものを識別して判断する前は、自由で分け隔てもない世界があったようです。
以前、友人宅を訪れたときのことです。久しぶりに会った夫妻と会話を始めるとすぐに、手持ちぶさたな二歳の息子さんが私の持つ扇子に興味を示しました。「これは扇子っていうんだよ」と手渡し、再び話に夢中になっているとあっという間に数時間が経っていました。さて帰ろうかと、その息子さんの方を見ると、まだその扇子を持ちキラキラした眼をして楽しそうに遊んでいたのです。「長い時間よく飽きずに遊んでたね」と言いかけて、ハッとしました。私は、扇子は暑いときに仰ぐもの、挨拶時に膝下に置くもの、何か受け取るときにお盆にするものなど、幾通りしか使い方が浮かびません。むしろそう思ってしまっているから、他に頭がいきません。しかし、その子はそんな区別をしませんから、扇子を広げたり話しかけたり、杖にしたり箸にしたり、きっと何千何万通りの遊び方をしているのです。そんな自由自在なはたらきが「ものがみんな溶けているせかい」なのではないかと、その子のキラキラした眼を羨ましく思いました。
さて、29歳で夭折した重吉は、残す妻子を心配し、胸に迫るような詩も多く残しています。自己の詩については、「赤ん坊の口から出なければうたわれぬようなものを目指している」とし、その究極に至れるのは「五十を越してからのことだろう」と友人への手紙に書いているそうです。安易な子どものままの心ではなく、苦労や精進を積み重ねた先に至る「童心にかえる」という境地なのだと思います。それは、厳しい修行を貫徹された祖師方にも通じることなのではないかと想像します。
まもなく春本番。自然の営みを通して、心の軽やかさを取り戻したり、自分自身の内面を見つめることが出来ます。童心にかえって驚いたり楽しんだりしながら日々を過ごしていきたいと思います。
富岡孝彰