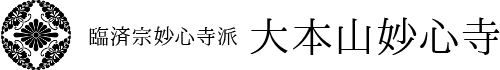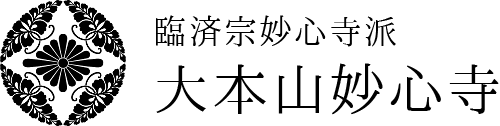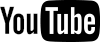092 いのちは誰のものなのか
以前、朝日新聞に生命科学者、柳澤桂子さんの「宇宙の底で」が連載されていました。そのなかに「いのちは誰のものなのか」という随筆がありました。
彼女は原因不明の病気を患いました。ベッドの上ではほとんど身動きできず、心臓近くの太い静脈にチューブを入れ、そこから栄養液を送り込みながら生命を維持されていました。激しい痛みと不整脈によって、七転八倒の苦しみの日々を送っているとき、自然のままならばとうに死んでいるのに、人工的に生かされていることと、病気に対する絶望感から、主治医に点滴を抜いてくれるよう頼みました。すると、そのときの家族の驚きと動揺は、彼女の予想をはるかに超えたものだったのです。それまでも、私のいのちは私だけのものではないという考えはあったものの、改めて家族の愛情の深さを認識したとき
「いのちはその人だけのものではなく、多くの人々の心の中に分配され存在している。分配された私のいのちは、その人のものである」
という思いに到ったのです。
一休禅師の辞世の歌に
いま死んだ、どこへもいかぬここにおる、たずねはするな、ものはいはぬぞとあります。釈尊が臨終のとき、これまで共に道を歩んできた比丘たちに対して
「不安がってはならない。泣いてはいけない。死は特別なことではなく、あたりまえのことなのだ。死はお前たちにも必ずおとずれるものだから、そのときのために怠らず精進していきなさい。汝等が邪な思いにうち勝ち、正しい道に励むとき、私は汝等の心の中にいる」と語られた最後の言葉を、一休禅師が端的に詠まれた歌です。
また、良寛和尚は、幼い子どもを亡くした母親が取り乱し、嘆き悲しんでいる姿を見て、そっと近づき小声でつぶやくように
「そう一度に泣いてしまわずに、毎日毎日少しずつ泣いてやりなさい」
と言われたといいます。亡くなったわが子のいのちを、自分の心のなかで温めしっかり抱いて、これからの人生をより豊かに生きていきなさい、という願いを込めてのことでした。
自分のいのちを思うとき、四十億年間途切れることなく続いてきたいのちであり、また家族や友人や多くの人々の心のなかに記憶として生きているいのちです。同事に自分の心のなかにも、多くの人々や他のいのちが生きているのです。
村上明道