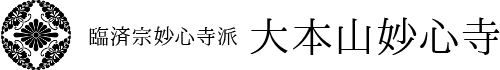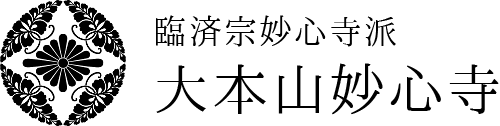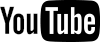薫風自南来 殿閣生微涼
中国 唐の十七代皇帝である文宗(809-840)が、五言絶句の起句と承句を詠みました。
人は皆炎熱に苦しむ
我は夏日の長き事を愛す
それを承り、政治家である柳公権(778-865)が一篇の詩にしました。
薫風、南より来たる
殿閣、微涼を生ず
(意訳)
多くの人々は夏の茹だるような暑さの日は得意ではない。けれど、私は夏の暑くて長い一日をこよなく愛している。
暑い最中に、庭や林を抜けて宮殿にそよぐ南風の涼しさは言葉に表せないほどよいものだ。熱気を帯びていた宮殿に、清涼がもたらされるようだ。
宋代の禅僧 大慧宗杲禅師がこの逸話を聞いて悟られたと伝わっています。禅師は何を感じ取られたのでしょうか。
この詩の茹だるような暑さは、現実世界で右往左往して、誰かと衝突し予期せぬ出来事で心が塞ぎ込み、忙しさで頭がいっぱいになっている私たちの世界を意味していると私は考えました。その中に生きていても、少しの薫風にきづく心の柔らかさがあれば、狭い家の貧乏暮しを苦ともせずに宮殿に住むような豊かさを得る事ができるという事だと思います。けれど、頭で理解しても現実はうまくはいきません。
大慧宗杲禅師は、頭だけで理解したのではなく、身心ともに気づかれて、自らに降りかかる出来事をしなやかに柔らかく受け止める心を感得されたのではないかと勝手に想像しました。
さて薫風とは、草木が芽吹いた季節の爽やかな風のことを意味します。私は薫風と言われると草花の青々とした香りを思い出します。
私が生まれ育って、現在副住職をしている浅草の寺は、東京大空襲で全てを焼失しました。私の祖父母が昭和四十年代に寺を復興した時、夏みかんや柿やイチジクなど多くの実がなる樹木を植えました。私が子供であった昭和六十年にはそれぞれに樹木が成長し、よく実をつけていました。しかし都心は空気が汚かった当時、飲食店の油の匂いが果実に付いてしまい、期待したほど美味しく食べることができなかったようです。
祖父母が亡くなって私が大人になる頃には、手入れが行き届かず、鬱蒼として樹木が混み合っていました。大学卒業後に修行道場に入門し、寺に帰ってからは多くの樹木を伐採して明るい庭になるように努めました。寺族にも檀家さんにも褒めていただきましたが、祖母が大切にしていた山椒の木を誤って折ってしまった時に、両親がとても残念がりました。
油臭い果実ばかり成る庭木のなかで、葉も実も香りが強いためか山椒の木だけは、油の匂いもせず美味しく食べることができ、晩春から盛夏まで毎日少しずつ食卓に上りました。
私が山椒の木を折ってしまったことは事実ですが、葉山椒はスーパーでも売っている、トゲがある種類であったため庭掃除の邪魔になる、わざとではないなどと思い、両親は私を許して忘れてくらたら良いのにと思っていました。しかし両親はホームセンターや植木市にいくたびに山椒の株を買ってきて植えるように言いつけました。祖父母の形見のように思っていたのかもしれません。ほとんどの株が庭の土に馴染んでくれず枯れてしまう中で、一株だけ成長を続けました。なかなか成長しませんでしたが、今年でようやく八年経ち、腰くらいの背丈になりました。
六月中旬のむせ返るような暑さの日、庭の草むしりをしていました。
編集を担っている布教誌の締切、小学校に進学した娘の悩み事や持病の不安など、気もそぞろで施餓鬼の準備に取り掛かっていました。本堂のすす払いをして窓を拭き、法要の支度をして、庭掃除に取りかかると庭中雑草が伸びていることに気がつきました。「めんどくさい、なんでこんな時に限って」とイライラしながら草をむしりはじめ、頭の中ではどのくらいの時間で庭全体の草むしりが終わるか計算し始めます。誰でも焦って物事に取り組んだとしても、うまく運ぶことはありません。それを知っていても焦って、知らず知らずに焦ることが癖づいてしまうものです。そして中途半端な結果ばかりで、自分でも納得がいかず、時には他人に注意されてしまいます。私も同じで、住職より「あまり庭が綺麗になっていない」と注意されました。思わずムッとして全体を見ようとして不意に立ち上がると頭を桜の枝にぶつけました。痛みにびっくりして前かがみになった時、青臭いほどの山椒の香りのついた風が身心を吹き抜けていきました。思わずハッとしました。この匂いの中で、毎日祖母と葉山椒を採ったことを思い出しました。
山椒の葉を枝から切るときは、毎日頂戴するものだからどの葉を切るかよく選んで、樹形に偏りがでないように。台所にもっていくまで、そぉっと持っていかないとすぐに悪くなってしまうよ。
子供でしたから、山椒にさほど興味があるわけではありません。けれど祖母は何事も丁寧にやらなくてはならないと常に私に叱っていました。
ドイツの作家 ミヒャエル・エンデによる児童文学『モモ』は、忙しさの中で生きる意味を忘れてしまった人々を描きます。主人公のモモは町外れに住み着いた不思議な少女であり、モモに話を聞いてもらうと、皆幸せな気持ちになりました。掃除夫ベッポもそのひとりです。ベッポの台詞に次のものがあります。
とっても長い道路をうけもつことがあるんだ。おそろしく長くて、これじゃとてもやりきれない、こう思ってしまう。そこでせかせか働きだす。どんどんスピードをあげてゆく。ときどき目をあげて見るんだが、いつ見てものこりの道路はちっともへっていない。だからもっとすごいいきおいで働きまくる。心配でたまらないんだ。そしてしまいには息がきれて、動けなくなってしまう。道路はまだのこっているのにな。こういうやり方は、いかんのだ。
いちどに道路ぜんぶのことを考えてはいかん、わかるかな?つぎの一歩のことだけ、つぎのひと呼吸のことだけ、つぎのひと掃きのことだけを考えるんだ。いつもただつぎのことだけをな。するとたのしくなってくる。これがだいじなんだな、たのしければ、仕事がうまくはかどる。こういうふうにやらにゃあだめなんだ。ひょっと気がついたときには、一歩一歩すすんできた道路がぜんぶおわっとる。どうやってやりとげたかは、じぶんではわからんし、息もきれていない。これがだいじなんだ。
やりたい・やりたくない、好き・嫌いで物事を判断せず、与えられた仕事をひとつひとつ丁寧に取り組んでいかないといけないという事を祖母は教えてくれたのだろうかと勝手に想像しました。
大人になるにつれ、いろいろなことを抱え込んで近い未来のことばかり考えて、今を過ごしています。私は山椒の強い香りのする風を感じて、三十年前に楽しく笑い遊んでもらった祖母のことを、同じ場所でふと思い出し、今更になって祖母の教えを理解した気がいたします。先のことばかり囚われるのではなく、目の前のことにまっすぐ取り組むことが何より大事で、少しでも人生を生きる術なのだと教えてくれていたような気がいたします。
山椒の香りは私にとっては薫風であり、鮮やかに祖母を思い出して涼やかな思いがしました。