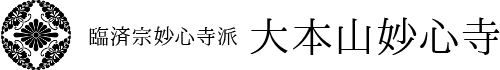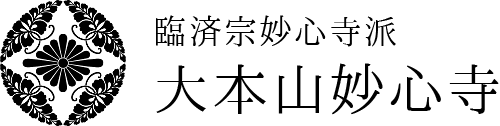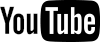心頭を滅却すれば火も自ずから涼し
毎日、猛暑が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
中国の唐代、臨済宗の宗祖である臨済義玄禅師が活躍されていた頃の詩人である杜筍鶴(846-904)が『夏日、悟空上人の院に題す』として詠みました。
三伏門を閉して一衲を披す
兼ねて松竹の房廊を蔭う無し
安禅は必ずしも山水を須いず
心中を滅得すれば火も自ずから涼し
三伏とは、暑さのもっとも厳しい時期を意味します。夏至の後の三回目の庚の日を初伏(現在の七月中旬)、四回目を中伏(同七月下旬)、立秋後の最初の庚の日を末伏(八月初旬)として、全て併せて三伏と言うのです。
酷暑の中で、悟空上人はお寺の門を閉ざして坐禅をされています。松や竹で堂宇が覆われているわけでない、炎天下の簡素な寺のなかで法衣を纏って坐禅をしている様を見ると、川面が見える涼しげで静かな山中でなければ坐禅に適さずということではないようです。
悟空上人のように、心中を滅得すれば(迷いや憂いを滅して、しなやかにものごとを受け止める心を見出せば)、暑さを分別することなく暑さとして単に受け取り、淡々と過ごすことができるのです。
時代が下り、宋代に圜悟克勤(1063-1135)によって編まれた『碧眼録』第四十三則に、転句と結句を引用されます。この則は、洞山良价禅師(807-869)に修行僧が「寒暑のない処はどんなところですか?(生きているものが避けられない苦を、承知の上でどのように避けますか?)」と訊いたところ、洞山禅師が「寒時は闍黎を寒殺し、熱時は闍黎を熱殺す(暑い時節には暑さになりきり、寒い時節には寒さになりきることが肝心だ)」と喝破される話です。その話を後世に生きた圜悟克勤禅師が、
安禅は必ずしも山水を須いず
心頭を滅却すれば火も自ずから涼し
(意訳)心静かに坐禅するのに山や河を必要とはしない。心を滅却すれば火も本より涼しい。
と引用します。
涼しく梅雨が長引いた六月から七月上旬、豪雨や台風に悩まされた七月中下旬、そして八月上旬は酷暑に見舞われました。天気予報に一喜一憂しながら予定をこなす毎日に疲れてきた土曜日の夕方、ふと外出すると浅草の街には浴衣姿の人が溢れていました。
隅田川の花火大会かと気づきましたが、寺で飼っている犬が吠えるな、明日は門前にゴミが捨てられているだろうな、どうせ高いビルに囲まれて見ることはできない花火に興味も示さずに暑い暑いと文句を言いながら生活していました。
大きな打ち上げ音の中、七歳の娘にせがまれて大通りのコンビニまでアイスクリームを買いに行くと、大通りに人だかりができて歓声が上がっています。次の瞬間、大きな花火が目の前に広がり、どうせ高いビルに囲まれて見ることはできないと決めつけていた私の心に色鮮やかに映りました。オリンピックの建て替えラッシュに伴って大きなビルが取り壊されたおかげで、きっと今年だけ観ることができた花火を町中の人が嬉しそうに見つめていました。
日に日に成長する娘を久しぶりに抱き上げて重さを実感し感慨深くなりながら、次々に上がる花火に心を奪われていました。思えば暑い日が続き、心ここにあらずで愚痴ばかりこぼし、迷った心がどこかにいってしまったようでした。鮮やかな花火と重くなった娘のおかげで、今を実感し、迷い彷徨う心を自分の身体に戻すことができたような気がいたします。
暑さ寒さをはじめ、自らに降りかかるものごとを、あれやこれやと考えていると、苦を大きくなるばかりです。「心頭を滅却する」とはそうした迷いを一旦忘れ去ること、「火も自ずから涼し」とは身に降りかかるできごとを受け入れ、鮮やかに生きていくことだと思います。
花火は、お盆に帰ってくる死者を弔う行事だとも云われます。それだけでなく、花火には暑さで迷い彷徨う人々の心を調え、ご縁を再確認するはたらきもあるのではないかと勝手に考えた次第です。