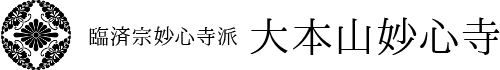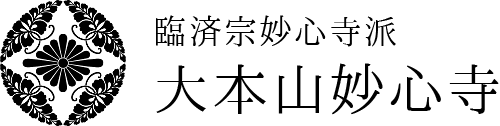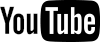【彼岸と中道】
岡山県真庭市 佛土寺住職 馬場 道隆
『暑さ寒さも彼岸まで』——三月の「春分の日」と九月の「秋分の日」を中心とした前後一週間は「お彼岸」と呼ばれ、寺院での法要やお墓参りなどの先祖供養が営まれる、日本古来より伝わる仏教徒にとって大切な仏道修行実践期間です。お彼岸の中日である「春分の日」「秋分の日」には太陽が真東からのぼり真西に沈み、昼と夜の時間がほぼ同じ(中間)になります。このことから、お釈迦様が説かれた「中道」の教えと結びつくようになり、「お彼岸」は「中道」の実践期間としても定着しています。
この「中道」の教えはひとことで言えば「かたよらない」ということです。何に「かたよらない」のか…それは「自分の都合や思い込み」に、です。ともすれば「中道」の教えは「人生可もなく不可もなく」「頑張りすぎず怠けすぎず」といった一個人のためだけに説かれた処世訓のようにも受け取られますが、本来の意味はもっと深いところにあります。誰しも考え方や身体能力に様々な違いはありますし、置かれた環境や立場によっても常に違いは生じてきます。そうすれば各々に「自分にとって都合よい状態」も多種多様に変化するものです。それを一人一人が主張し押し通そうとすればどうなるのか…他者の痛みを知ることも思いやることもなく人間社会は崩壊の一途を辿ること火を見るより明らかです。「中道」とは一個人の都合よい状態や平穏安寧だけを求めるための教えではなく、沢山のご縁によって生かされている自分自身に気づくための教えです。自分を活かすことがそのままに他者を活かす生き方、日常生活における「調和」を模索していくための道標となるのが「中道」の教えです。
お釈迦様はその生誕時に七歩すすんで「天上天下唯我独尊」という言葉を発せられた、という有名な逸話があります。また中国唐代の禅僧・百丈禅師は「如何なるかこれ奇特の事(この世の中で最も有難く素晴らしいことは何ですか)」という問いかけに対し「独坐大雄峰」と応ぜられた、といわれています。この二つの語、決して他者を見下すような強い自尊心の表れから発せられたものではありません。この世の中で「私(独)」というたった一人の人間のために何百何千何万といういのちの関わりや繋がりがあってこそ生きてこられているということ、つまりは一人勝手に生きているのではなく、数多のいのちの支えがあってこそ今私はここに「生かされている」、その大きな感動から発せられた語であるのです。
コロナ禍によって人間の生活環境は大きな変化を求められました。人間本位・人間ありきで進められていた思考や活動の多くが見直し変更を余儀なくされています。葬儀や法事に関しても現在飛沫感染を防ぐために人数制限や食事提供しないよう配慮がなされています。「家族葬」や「略式葬」はこの風潮を追い風に更に加速度を増すのではないか、とも言われています。葬儀は故人が数多のご縁に対し最後の感謝を伝える場であり、また法事は故人が紡いできたそのご縁に感謝する場、それができないことは私自身一僧侶として務めていく上でもとても心苦しく感じます。「今を生かされている」という自覚は、文章や映像などから得る知識だけではなく、やはり体感し経験していくものがなければならない、と思うからです。修行僧時代には様々なことが思い通りにならず他者との比較をして惨めな思いを抱き卑屈になること多々ありましたが、いざ世間に出てみればもっと沢山の思い通りにならないことで溢れており、人の心の痛みや悲しみを理解することは文章や映像で得たうわべの知識だけでは通用しない、その身を以て重ねてきた修行経験に常に立ち返り務めていくしかないのだ、ということに気づかされました。
なんと有難いことに日本には春と秋の二週間も「お彼岸」という自分自身を見つめる実践期間があるのです。このことを強く再認識して、単なる休暇期間になどせず、先祖供養を通して数多のご縁の「中(道)」に自分自身が今生かされていることを自覚し、日常生活の在り方を正していく期間としていくことが大切でありましょう。今この時、あたりまえにしていたことすべてが実はあたりまえのものではない、ということに気づけば、次の一挙手一投足はおのずとどうするべきかはっきりと見えてきます。コロナ禍「終息」への道標もきっとそこにあるはずです。
了